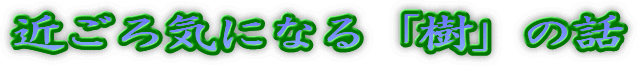
その日、
子供がテレビをつけると
珍しく『ほんパラ!関口堂書店』という番組でした。
そして、ちょうど
「グリーン・ファーザー
インドの砂漠を緑にかえた日本人・杉山龍丸の軌跡」
という本を紹介していました。
何かピーンとくるものがあり、
背中で聞いていた私も途中から子供と並んでテレビの前に座りました。
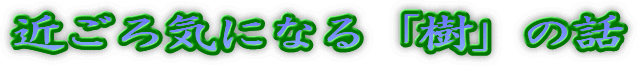
その日、
子供がテレビをつけると
珍しく『ほんパラ!関口堂書店』という番組でした。
そして、ちょうど
「グリーン・ファーザー
インドの砂漠を緑にかえた日本人・杉山龍丸の軌跡」
という本を紹介していました。
何かピーンとくるものがあり、
背中で聞いていた私も途中から子供と並んでテレビの前に座りました。
杉山龍丸(たつまる)
恥ずかしながら、一度も聞いたことのない名前でした。
番組で紹介された杉山龍丸氏とは・・・
| 昭和36年(1961年)11月、インド マハラストラ州ベドチイ村で行われる、 ガンジー翁の弟子たちの大会「サルボダヤ・サンメラン - すべては立ち上がる」に招かれて、 龍丸は初めて渡印した。 インドの窮状を知り、家族を残してインドに赴くと、 その困窮の凄まじさと、国を良くしようと願う人々の熱意に打たれ、 貧困と飢餓の克服のためできる限り尽力しようと誓う。 そこで、まず砂漠の緑地化を進言し、現地での実験と指導を始めた。 真っ先に国際道路の両側に植えたのがユーカリ、 ヒマラヤ山脈から流れ出る地下水脈を集め保水目的で ユーカリ(砂漠植物)を植え、 植物の根により水の確保をすることを考えたという。これがまさに 緑のダム 現地の人々の理解と協力を得るまでに大変な苦労があったが、 ひとたび人心をとらえるや、 この植樹事業は着々と実を結び、 後に米や野菜などは気候に恵まれ三毛作ができるまでになり、周辺地域での農業を着実に実現していった。 そして、約10年という歳月が流れ、 この成果が認められ、更にインドの別の地(シュワリック)で緑化の協力を求められることなった。 またしても、この地でも別の苦労が待っていたのだが、 見事にクリアし砂漠を緑豊かな土地へと変えることに成功した。 生涯に植えた木は3万本とも言われ、 その業績をたたえて杉山龍丸氏はグリーンファーザーと呼ばれているそうである。 オーストラリアで行われた、第二回国際砂漠会議に出席してその成果を発表する機会は与えられたが、 日本からはたった一人での参加だった。 龍丸はこの会議に出席するために友人から50万円ものお金を借りなければならいほどの経済状態だったという。 が、ここまでの成果をもってしても日印両国政府などの経済的援助も得られない事業だった。 何ゆえ祖国に家族を残し、先祖伝来の農園などの広大な土地をすべて売り払い、借家住まいまでして資金をつくり、 異国インドで苦難の事業をなしえたのか? それは、一つには杉山家3代にわたるエピソードに残されているとおり、 国家のありかたやアジアの自主独立、農業指導者養成への夢のバトン、 もう一つは、戦争中体験した衝撃的な1シーンによるものと紹介されていた。 |
この本の紹介の後、
一つの質問が出、出演者が答えます。
| Q. 龍丸氏は外国人の訪問を受けると、必ず連れていき見せた場所がありました。 それはどういう場所でしょう? |
私は、意外にもすぐさまその場所が浮かんだのですが、
さて、あなたはいかがでしょうか?
回答者には4択でヒントが出されていました。
| ヒント 1. 学校の校庭 2. 神社 3. ゴルフ場 4. 何でしたっけ?? |
これならお分かりでしょう。
正解は 2.の神社でした。
理由は
龍丸氏の言葉によると、 「日本では、昔から森を大切にしてきた。その象徴が、全国の神社の森、つまり 鎮守の森だよ。日本の水がきれいなのは、山や野に、木があるからだ」 外国からのお客様がくると必ず森を見せて説いて明らかにされたという。 このエピソードは、龍丸氏が本格的にインドでの植林作業にたずさわる前のことだった。 また、 龍丸氏が初めてインドに渡りパンジャップ州の総督パトラマ・タヌ・ピラト氏に招かれた際、 インドの生活を豊かにするためにどうしたらよいか、日本とインドとの違いを聞かれて 植林による治山治水をあげている。 他に、 古代文明以来、特にアシューカ王は仏教を盛んにし、建造物を作ったが、 そのほとんどが薪の火によって焼かれたレンガを使って築いたため 野や山の森林が次々と消えていった。 また、デリーにおこったイスラム教の王朝たちは多くのモスク(寺)を建設しているが、 モスクのまわりの森林をことごとく伐採していったことで、 大地の水がなくなり、地面は乾燥し、砂漠になっていった と指摘した。 それに比べ、日本の神社は!! |
わが町 常滑 の

私がすぐさまおもい浮かべられるのは
| 1.多賀神社 (常滑市苅谷) 2.神明社 (〃栄町) 3.本宮神社 (〃樽水町) 4.常石神社 (〃奥条) 5.御嶽神社 (〃白山町) そして、昨年知った 6.海椙【うすき】神社 とすぐ隣の 三楠八幡神社 (〃森西町) が思いついたところです。 |
| 7.瀬木御嶽神社 (〃千代・乙田との堺) 8.北条御嶽神社 (〃千代・乙田との堺) 9.中宮 (〃奥条 大善院) 10.榎戸神明社 (〃神明町) |
北の地理にうとい。
11.矢田八幡神社 (〃矢田谷海道)は?
12.久米八幡社 (〃久米東郷)は?
大野へ向かう途中の海側に神社があったが、確か森はなかった。
いや南の地理にもうとかった。
10.松尾神社 (〃坂井天王)は?
とにかく、わが半島のわが町の
鎮守の森は大丈夫か???
こんな、大仰な言葉にびっくりされる方が大半でしょう。
ところが、なのです。
これらの鎮守の森までもが大変なことになりつつあるのです。
一体、どの神社にどんな問題が起ころうとしているか、ご存知でしょうか?
とりあえずは6択です。
正解の1つは
| 2. の 神明社です。 |
| ・・・ 昨日常滑市民文化会館の地下駐車場に車をとめられず、競艇場の駐車場を利用しました。 ふと、見上げると神社と木々がくっきり 「あれって神明社よねぇ。鎮守様よねぇ」と友達に確認しました。 そして、二人で「あの神明社をくずして移転しようなんて、考えられる?」と ほぼ同時じ同じようなことを言葉にして顔を見合わせました。 もちろん神明社がそんなことになるとはありえないことと思いましたが、 ・・・ |
すると
| 神明社はいま、がけの補強工事が国の急傾斜地崩壊対策事業で進められています。 そして、おそらくここ10年の内に瀬木線の拡幅工事で今の鳥居の所まで道路になってしまいます。 そうなると境内の確保や拝殿まで上がる道路やらで、多くの人の知恵が必要です。 ・・・・ 一般では宗教だからと言ってかかわりあいにならない方もおりますが神様がおるとか、おらんとかじゃなく正月から大晦日まで先祖が大切にしてきた行事を季節の節目節目を通して、自分への反省点と出発点の気構えと思って自分自身のなかで自分との約束をする思いをこめて拝殿に向かって祈っていただきたいですね。 そういう、意味から子供のころから遊ばせてもらった鎮守の森を後世に立派にして伝えていきたいです。 |
正真正銘
受難 の神社がもう一つ
それは
| 6. の 海椙【うすぎ】神社です。 |


| 近ごろ気になる「樹」の話 -その2- さらに82億円投入の土地区画整理事業と海椙神社移転計画 |
H14.4.12UP |
| 元治元年(1864年)〜 昭和10年 |
杉山茂丸、明治維新を憂い伊藤博文に直訴。アジアの開発と日本近代化のために金策、日本興業銀行の基盤。インドの独立をめざすラス・ビハリ・ボースが日本に亡命、かくまう。中国の孫文やインドの詩人タゴールを支持 |
| 明治23年(1889年)〜 昭和11年 |
杉山泰道、茂丸の命を受けアジアの農業指導者養成のため、約4万坪の土地(杉山農園)を購入。 農業のかたわら、夢野久作のペンネームで戦争賛美に流されず、人間としての魂のあるべき姿に迫る小説を執筆 |
| 大正8年(1919年)〜 戦後まもなく |
杉山龍丸、3歳より鍬を持ち、杉山農園と祖父茂丸・父泰道の遺志を継ぐ。 友人との出会いにより、日本から資金や青年の教育にあたるなどインド支援に協力 |
| 昭和30年(1955年) | インドのネール首相からの特使より「産業技術の指導支援の依頼」 |
| 昭和36年(1961年)11月 | 龍丸、初めて渡印 |
| 昭和38年(1963年) | 渇水が続きインドの大飢饉、後3年間も続き500万人もの死者 |
| 昭和47年(1972年) | 砂漠地帯に生え、葉も花も実も食用になり生長が早いモリンガの木を発見。インド全土を救う |
| シュワリック・レンジ(丘)の崩落を食い止めるためにサダバールという植物を使う。 この植物はインドでは水や土の中の栄養分を吸収してしまうとして農耕に害があると言われ、家畜も嫌って食べない植物だった。しかし、砂漠地帯ににも微生物や苔や草が生きていることを発見。木とも草ともつかぬサダバールという植物を挿し木して表面を安定させ、その後にユーカリを植えて緑化に成功している。 |
|
| 昭和54年(1979年) | インドの地元の新聞に「3万本の木を植えた日本人」として紹介される |
| 昭和59年(1984年) | オーストラリアで行われた第二回国際砂漠会議に出席。 「私たち人類は、近代文明を作り、自然を克服したと考えている。しかし、ほんとうに自然を克服したのであろうか? そこに、砂漠化の問題があるように思う。 この砂漠の緑化の問題は、自然の中に一本、樹を植えることに始まる。 誰でもできるし、具体化できることである。 人間は、食料、酸素、水が無ければ生きられない。それらは、樹、植物によって培養され、作られている。 自然の恵みに応ずることを忘れて、人間として生きられるのであろうか?」 と前置きし、その成果を発表 『砂漠緑化に挑む』を執筆 |
| 昭和63年(1988年)9月 | 病没 |